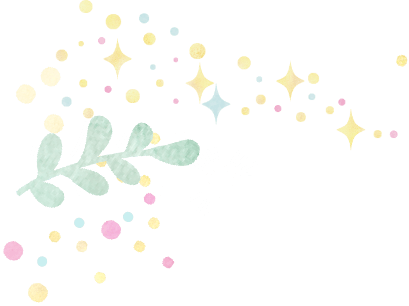
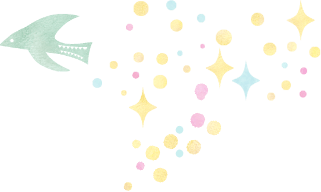

同じ3歳の息子をもつ者として、このニュースを知ってから胸の痛みが治まりません。
今後、警察の捜査や裁判によっていろいろなことが明らかになり、
同じことを繰り返さないために何らかの対策が新たに取られるのかもしれません。
ただ、3歳の男の子が、想像を絶するような苦痛を感じ、そのまま命を絶たれたという事実が覆ることはありません。
嬉しい、楽しい、悲しい、苦しい。好き、嫌い。
3歳の息子を見ていると、すでにたくさんの感情を持ち、
自分の望む状態を得るために頭を使い、自分の言葉でそれを表現する力も持っていることが分かります。
身体は小さくても、確実にひとつの人格をもち、
幸せになるために産まれてきた存在です。
どうしてこんなことになってしまったんだろう・・・
我が子の可愛い笑顔、柔らかい肌に触れるたびに、
同じ年齢の子が感じざるを得なかった苦痛や恐怖を想像し、
苦しくてたまりません。
児童虐待が起こるたびに、児童相談所の対応が問題視されます。
今回も、周囲が危険を訴えていたにもかかわらず、
男の子を守ることができなかったため、児相の対応を批判する意見も少なくないようです。
「面談して大きな問題がないことを確認した」
「緊急性のある事案には該当しないと判断した」
というのはよく聞く言葉ですが、
これを聞くと自分が研修医の時の救急外来を思い出します。
救急外来は、やってきた患者さんの「緊急度」を判断し対応する場所です。
大した事ない軽症の人もいれば、命にかかわる状態の人もいます。
一番悩ましいのは「軽症そうに見えるけど、じつは今後重症になり得る人」の判断。
もし医師が緊急度の判断をあやまり、本来であれば入院が必要なのに自宅に帰してしまった場合、
患者さんの命が失われたり、状態を悪化させてしまう可能性があります。
そうなると、場合によっては病院や医師が訴えられ、罪に問われるケースも出て来ます。
つまり、患者さんに不利益を与えないことが最重要ですが、
医師が自分の身を守ることも非常に重要になってきます。
そのためにも、医療の現場では様々な「判断基準」が設けられます。
バイタルサインといった身体の状態や、その人のリスク因子(年齢、持病、喫煙etc)、
また「〇〇といった症状があるかどうか」といった緊急度の高い症状の様子などなど
こういった基準をもとに考えたうえで、
「あなたは入院した方がよい」
「あなたは自宅で様子見でよい」
と判断し、
もし「帰宅」した人が、その後急変してしまったとしても、
「基準に沿って判断した」のであれば医師に落ち度があったと認定されるリスクを低減することができます。
「少しでもリスクがあるなら、大事をとって入院させればいいのでは?」
と思うかもしれません。
ただ、病院のベッドには限りがあり、(私の勤めていた病院では)研修医に入院を決める権限がなかったため、
入院させるとなると、上級医に来てもらってお願いする必要がありました。
特に夜遅い時間は、そのために当番の上級医を起こしたり、病院まで呼び出す必要もあり(時にはとても不機嫌で、理不尽に怒られることも。。。)
ベッドの調整や家族への説明など、かなり手続きに手間と時間がかかることもあります。
つまり、入院のハードルはまあまあ高いため、簡単に「とりあえず入院しとく?」とはしにくい状況でした。
おまけに、めちゃくちゃ忙しい日は、頭も手もうまく回らず、(疲労や眠気も相まって)
「軽症の人をいかに手早く診察して帰宅させるか」
を目標にせざるを得ない時もありました。
そうなると、
「訴えられない、最低ラインだけ守っておけばいい」
という思考になるのは避けられません。
当たり前のことですが、
「今」が重症でないからといって、
「今夜」「明日」「1週間後」
も無事である保証はありません。
実際に、入院の必要なしと判断して帰宅させた後に、
急変して運ばれてくるケースも時々あります。
逆に、
「この人、基準的には軽症だけど、何かおかしい・・・」
と感じ、追加の検査をしたら大きな病気が見つかり即入院となったケースもあります。
本来であれば、「基準」は最低限守りつつ、
「だけど、この人なにか気になるからしっかり検査しておこう」
「家族の心配も強いし、念のため1泊入院してもらおう」
といった、一歩踏み込んだ対応ができるのがあるべき姿だと思います。
しかし、あまりに忙しい状況、人手不足、また残念ながら医師の倫理観不足というケースもあり、
「入院させていれば救えた命」が生じてしまっているのが現状です。
この状況を改善するには、
・医師の労働状況の見直し
・医師不足(偏在)の解消
・医師への倫理面の教育
・入院しやくする仕組みづくり(私の病院の場合は研修医に入院権限を与えるなど)
など、たくさんの複雑に絡み合った課題解決が必要です。
児童相談所の事情に詳しいわけではありませんが、
似たような課題があるのだろうと推察します。
病院を充実させれば、病気や怪我で苦しむ人がいなくなるかというと、
そうではありません。
そもそも病気や怪我をしない(しにくい)仕組みをつくる必要もあります。
同様に、児童相談所を充実させれば、虐待に苦しむ子どもがいなくなるわけではなく、
虐待をしない・されない社会にするための取り組みも必要不可欠です。
ただ、「苦しい」「助けて」という患者や子どもの最後の砦である、
病院や児童相談所は、
そういった人々を一人残さず救える施設でなくてはならないと思うのです。
自分には何ができるんだろう・・・
とずっと考えています。